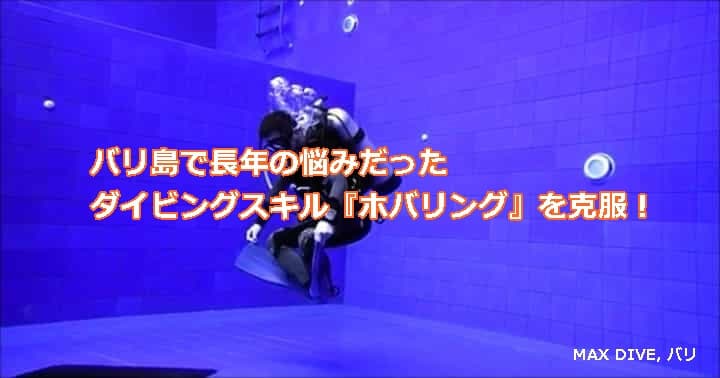バリ島でピーク・パフォーマンス・ボイヤンシー・コースに参加|中性浮力を徹底練習
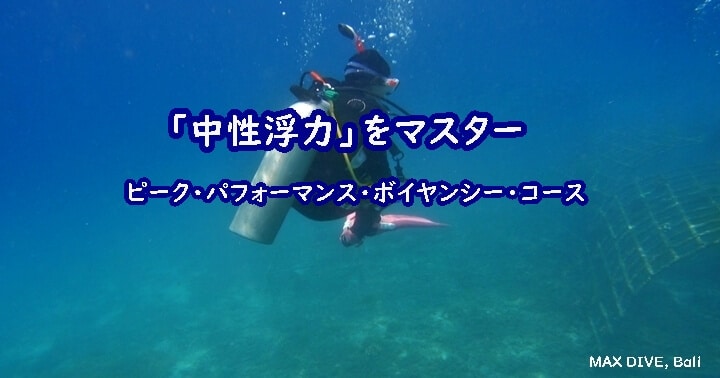
水中でカッコよく泳いだり、思い通りにピタッと静止できたら、ダイビングがさらに楽しくなりますよね。そのために重要なスキルが「中性浮力」です。ダイビングをする上で最も大切なテクニックの一つであり、上級者と初心者の大きな違いを生む要素とも言われています。
中性浮力とは、水中で浮きも沈みもしない状態を指しますが、多くの人にとっては自然に身につくものではなく、意識的に練習しないとなかなか習得できないスキルです。しかし、意識してダイビングすることで、中性浮力は誰でもマスターできます。
中性浮力をうまく取るためのコツは、適正ウエイト量の調整や、呼吸による浮き沈みのタイミングを理解し、上手に調整すること(肺のトリム)です。これらを意識的に実践すれば、水中でのバランス感覚を身につけ、誰でも中性浮力をマスターできます。 一度体で覚えれば、忘れることはありません。
もし以下のような悩みがあれば、中性浮力を見直すことが解決のカギになるかもしれません
- 水中でうまくバランスが取れない
- 潜降時に足が浮いてしまう
- 水中でピタッと静止できない
例えば、コースに参加したCさんのように、「上級者向けのダイビングスポットに挑戦したい」と考えているダイバーは、中性浮力のスキルを見直すのも良いかと思います。
今回は、Cさんが参加したピーク・パフォーマンス・ボイヤンシー・コースを通じて、コース内容と中性浮力の練習方法を紹介します。
「ピーク・パフォーマンス・ボイヤンシー・コース」って何するの?
PADIピーク・パフォーマンス・ボイヤンシー・スペシャルティ・コース(PPB)はPADIスペシャルティ・コースの1つで、レクチャーと2回の海洋実習ダイブを通して中性浮力のスキルを徹底的に学びます。
具体的には、シリンダー、スーツの種類や体型に合わせたウエイト量の調整方法から、BCDや呼吸による浮力コントロールのコツまで、さまざまなスキルを詳細にマスターします。そして、最終的には水中で思い通りにピタッと静止すること(ホバリング)ができるようになることを目指します。
- 適正ウエイトでの潜降と浮上テクニック
- フィンピボット
- 中層でピタッと静止するホバリングスキル
- 泳ぐ姿勢とフィンワーク
受講するメリットは?
ピーク・パフォーマンス・ボイヤンシー・コースを受講する最大のメリットは、水中でバランスよく動けるようになることです。これにより、エアの持ちが向上し、無駄な浮力の調整が不要になってダイビングがより効率的に楽しめます。また、バランスよく動けることで、水中環境を傷つけることなくダイビングを行えるようになり、自然への配慮も深まります。
さらに、中性浮力をうまく取れるようになると、ダイビングの幅がぐっと広がります。例えば、中層での安全停止がスムーズに行えるようになり、より安全で快適なダイビングが楽しめるようになります。こうしたスキルは、上級者向けのポイントへの挑戦にも大いに役立つでしょう。
苦手なスキルを解決|中性浮力習得法
ダイビングを始めると、さまざまな場所に行ってもっと深く探索したくなりますよね。オープン・ウォーター・ダイバーの段階では比較的簡単なポイントで潜っていても、アドバンス・ダイバーになると、もっとダイナミックでチャレンジングなポイントに挑戦したくなるものです。
しかし、「自分のスキルで大丈夫かな?」と不安に感じることもあるでしょう。そんなときは、一度インストラクターと一緒に、自分の苦手なスキルを見直してみることをおすすめします。
苦手を克服し、ダイビングのスキルをアップさせることは、上達への近道です。
Cさんが参加したピーク・パフォーマンス・ボイヤンシー・コースを通じて、実際にどのように中性浮力を習得したのか、苦手なスキルごとにどのように解決していったのかを紹介します。
苦手①:バランスよく泳げない|適正ウエイトと位置
Cさんの適正ウエイトは3キロで、BCD一体型のウエイトシステムを使用しています。
普段は、右に2キロ、左に1キロ装着していましたが、今回は右左1キロつづに変え、残りの1キロはシリンダーに付けて潜ってみました。この変更がバランス的に良かったみたいです。
理想的なウエイトのバランスは、左右1.5キロが最適ですね。
水中でバランスよく泳ぐには、自分の適性ウエイトを知り、ウエイトの位置をバランスよく調整するのが大切です。オーバーウエイトはNG
オーバーウエイトはNG
よく見かけるのが、「潜降しにくい」「体が浮きがち」といった理由で最初からオーバーウエイトで潜る人ですが、これは不必要な労力を使うだけでなく、安全面でも問題があります。ウエイトの量はダイバーの体型、使用するウエットスーツやシリンダーの種類によって異なるため、適切に調整することが重要です。
苦手②:潜降する時に足が浮く
Cさんは潜降中に足が浮いてしまい、普段は頭から(ヘッドファースト)潜降しています。潜降時にもたつくと、他のダイバーに迷惑がかかるため、この方法を選んでいたのです。しかし、今回はフィートファーストで潜降する練習をしました。
ウエイトの量と位置に問題はありませんが、Cさんは重いゴムフィンを着用しているのに、シリンダーとお尻が下り、足が浮いてしまう状況でした。
緊張すると体に力が入ってしまい、なかなか沈むことができません
ヘッドファーストで潜降する場合もありますが、まずはィートファースト潜降する基本スタイルをマスターした方が良いですね。
緊張せず、リラックスした状態でBCDの空気を完全に抜き、ゆっくりフーっと肺の中の空気を吐き出します。そうすると、自然と沈みます。Cさんの場合は、少し前傾姿勢を意識し、足が前に上がらないよう注意しながら潜降することもポイントでした。
苦手③:水中でピタッと止まれない(ホバリング)
ホバリングは、水中で浮きも沈みもしない状態を作り出し、手足を使わずに静止するスキルです。
まずは、オープン・ウォーター・ダイバー・コースでも練習した、中性浮力の練習法(フィンピボット)
の練習。

息を吸ってから体が浮いてくるまで時間差があります。直ぐには浮きません。
息を吐いてから体が沈んでくるまでも同じです。直ぐには沈みません。
このタイミングをしっかり体で覚えてしまいましょう!
※バリで苦手だったホバリング・中性浮力を克服
今度は、逆立ちにも挑戦

ホバリングも克服


苦手④:正しい姿勢で泳げてる?
Cさんの次の課題は、正しい姿勢で泳げているかどうかでした。まずはアーチ形のオブジェをくぐり抜ける練習を行いました。
最初の挑戦では、足が浮き気味になり、フィンがアーチに当たってしまいました。水中での姿勢をうまく調整できていなかったため、思うように進むことができませんでした。しかし、2回目の挑戦では、中性浮力を意識しながら正しい姿勢を保ち、見事にアーチをくぐり抜けることができました。


また、浅場のサンゴの上をダイビングする練習も行いました。
1本目ではフィンが浮き上がってしまい、うまく進むことができませんでしたが、2本目では正しいトリム(体勢)を意識してダイビングすることができました。これにより、バランスを保ちながらスムーズに泳げるようになりました。
フィンの使い方は、その場の状況に応じて変わることがありますが、まずは基本をしっかりマスターすることが大切です。正しい姿勢とトリムができるようになることで、水中での動きがより効率的で快適になります。


まとめ:「意識してダイビング」中性浮力の感覚を体で覚えこもう!

初めからパーフェクトな体制でダイビングできる人は少ないものです。中性浮力をうまく使いこなすためには、コースで学んだ知識やスキルを毎回意識しながらダイビングすることが重要です。それが上達への早道になります。
フィンの使い方も、状況に応じて変わることがあります。ベテランダイバーの動きを参考にしたり、アドバイスをもらうことも効果的です。
中性浮力のコツをしっかり掴み、毎回意識してダイビングすることで、水中でのバランス感覚が自然と身につきます。こうした感覚は、一度体で覚えると忘れることはありません。
Cさんも、近い将来「水中で自由に静止したり、カッコよく泳いでいる」自分に気づく日が来ることでしょう。