ブラックマンタ|マンタが黒くなる理由とその謎を解く

バリ島ヌサペニダのマンタポイントでひと際目を引くのがブラックマンタ!
背側だけでなく、腹側まで黒い部分が多いマンタです。


何で腹側が白いマンタと黒いマンタがいるの?



ブラックマンタ(メラニズム・マンタ/Melanistic Manta rays)は、体内のメラニン色素が過剰につくられて黒くなったんだよ。
メラニズムは陸上動物では見られまですが、魚類ではっきりメラニズムが確認されているのはマンタだけ。
それでは、
ブラックマンタはなぜ黒いのか?
彼らの生息地、生存率、色が与える影響などを深堀し、ブラックマンタの不思議を紐解いてみよう!
メラニズムってなに?
メラニズム・Melanism(黒色素過多症)は、メラノフォアと呼ばれる体内のメラニン色素を生成する細胞が過剰に活性化され、結果として毛や体が黒くなる状態を指します。この過剰な活性化は、メラノコルチンによる体内のメラニン色素(黒色素)が過剰生成によって引き起こされます。
体内のメラニン色素が欠乏するアルビニズム/アルビノ(先天性白皮症)の逆です。
陸上では「メラニズム」の動物はさほど珍しい存在ではありません。
代表的なのがクロヒョウ、黒猫、黒いネズミ、黒い鶏、黒いウサギや黒いウマなど。





黒い野生ネコをまとめて「ブラックパンサー」って呼ぶよね
海に生息する数百種の軟骨魚類のうち、今のところはっきり「メラニズム」の特徴を示すのは2種のマンタだけです。
ちなにみ、マンタはオニイトマキエイとナンヨウマンタの2種類います。
マンタの黒化(メラニズム)はどちらにも発症します。
(マンタについて詳しくはこちらのブログをご覧ください:マンタってどんな生き物?)




魚の体色とメカニズム
魚には最大で6つの異なる色素細胞が存在します。
これらの色素細胞は相互に影響し合い、異なる魚の種に多彩な色と模様をもたらす重要な役割を果たしています。
| 色素細胞の種類 | 役割 | |
|---|---|---|
| Melanophores(メラノフォア) | 黒色素胞 | 黒や茶色の色素の源であるメラニンを含み、 濃い色彩を生成 |
| Xanthophores (キサントフォア) | 黄色素胞 | 黄色やオレンジ色の色彩を生成 |
| Erythrophores (エリスロサイト) | 赤色素胞 | 赤い色彩を生成 |
| Lridophores (イリドフォア) | 虹色素胞 | 反射板を含み、銀色・虹色や金属的は光な光沢を生成 |
| Leucophores (リューコフォア) | 白色素胞 | 白い色彩を生成 |
| Cyanophores (シアノフォア) | 青色素胞 | 青や緑の色彩を生成 |
また、遺伝子の異常により、魚類にはさまざまな色素異常が発生します。
メラニズムはその一つの例です。
| 色素異常 | 例 | |
|---|---|---|
| Melanism: メラニズム(黒色素過多) | メラニン色素の過剰発生により、体や毛が黒くなる | ブラックマンタ |
| Albinism: アルビニズム(白皮症) | メラニン色素の完全または部分的な不在 により、体が白色になる | アルビノコバンザメコ |
| Leucism: リューシズム(白変種) | メラノフォアだけでなく、さまざま色素の減少により、体、皮膚や鱗が不規則に白くなる | ホワイトマンタ ホワイトハンマーヘッド |
※参考:New additions to black and white fish mutants
メラニズムのマンタは謎だらけ
メラニズムのマンタについては、未だ解明されていないことばかりです。
The Royal Society Journal にとても興味深い研究結果が発表されいました。
マンタの謎を研究するにために、科学者たちは、2003年から2018年の間にインド洋と太平洋のさまざまな場所でダイバーや水中写真家によって撮られた数千枚もの写真を使い、メラニズムの調査を行いました。
結果、オニイトマキエイとナンヨウマンタの両種の個体群で、
- 黒化したマンタが多くいる地域とそうでない地域がある
- 黒化したマンタは、一部の個体群で多く見られる
- 典型的なマンタと黒化したマンタに生存率の違いはない
- マンタの黒化と捕食は関係ない
- 表現型と地理的距離の間に関連性を発見
これらは、なにを意味しているのでしょうか?
メラニズムの発生する頻度と地域
メラニズムは一部の個体群でより一般的にみられ、多くいる地域とそうでない地域があります。
彼らの研究では、マンタの黒化はオニイトマキエイ(ジャイアント・マンタ)よりナンヨウマンタに多く見られました。
驚くことに、メラニズムはラジャアンパットの40.7%のナンヨウマンタの個体群でみられました。
ジャイアントマンタ(オニイトマキエイ)でメラニズムが発生する比率はエクアドルで多く見られましたが、
インド太平洋地域では2.5%以下です。
| ナンヨウマンタ | 個体数(全体) | メラニズム頻度(%) |
| ラジャアンパット | 712 | 40.7 |
| ヌサペニダ | 685 | 9.6 |
| コモド | 1176 | 9.9 |
| 日本 | 305 | 0.7 |
| モザンビーク | 1226 | 0.1 |
| ハワイ | 290 | 0 |
| ジャイアントマンタ | 個体数(全体) | メラニズム頻度(%) |
| エクアドル | 2007 | 16.4 |
| ラジャアンパット | 267 | 2.3 |
| ミャンマー | 131 | 2.3 |
| タイ | 344 | 0.9 |
| モザンビーク | 291 | 0.7 |
なぜ、メラニズムは一部の個体でより多くみられ、地域によって発生頻度の違いが生じるのでしょう?
メラニズムは進化上、長所なのか短所なの?


多くの陸上動物にとって、「メラニズム」は彼らの進化になんらかの利点を提供していると考えられています。
- 体の黒さが保護色となること
- 体の黒さが温度調節なので点で有利
例えば、黒いネズミが隠れるのを助けたり、ヘビが体温を調節したり、昆虫が病気に抵抗したりするのに役立ちます。
ブラックマンタはどうでしょう?
カウンターシェ―ディンはマンタを捕食者から守る役割をしているのか?




表層を泳ぐマンタは、光が当たる背中部分を暗い色にし、影となる部分を明るくすることで海と空の両方にカモフラージュすると言われてます。(※カウンターシェーディング)
捕食魚が下から見た場合、同時に見える海面が光って腹側の白色が保護色になる。
また、背中の黒色は上から狙われた時に、暗い海底と同化して見えにくくするため。



お腹側が黒いブラックマンタは敵から丸見えだね?
私達には目立たないように見えますが、実際には、暗い色は捕食者にとってより目立ちやすくなる可能性もあります。
その謎を解くため、
研究者たちは典型的なマンタと黒マンタの生存率の違いを調べました。
マンタの色と生存率の違い
They Royal Societyに発表された調査結果では、
両種の個体群間で生存率の違いはほぼ見られませんでした
インドネシアのコモド、ラジャアンパット、ヌサペニダにいた典型的マンタも黒化したマンタも生存率はほぼ同じでした。
海中で大きなマンタを襲う捕食者は限られています。
主に、大型のサメかシャチぐらいでしょうか。
黒化したマンタは、カモフラ―ジュが少ないにもかかわらず、捕食者は通常の色のマンタより黒マンタを標的にしなかったのです。
マンタにとってカウンターシェアリングによるカモフラージュはあまり意味をなさないようです。
MMF のグローバル マンタ レイアンドレア マーシャル博士
MMFグローバルのマーシャル博士は、この結果を見て「捕食がこれらの個体群の黒化に影響を与えないことを示唆している」とコメントしています。
現在の研究では、メラニズムはマンタの生存に有利でも不利でもないと結論付けてます。
Preziの記事によると、マンタの進化は、カモフラージュが発達し、毒針を失い、平らになって大きくなったと考えられいます。
もし、メラニズムがマンタの生存率に関係なければ、従来の進化説は変わるのでしょうか?
メラニズム(黒化マンタ)は偶然によって広がっていった?
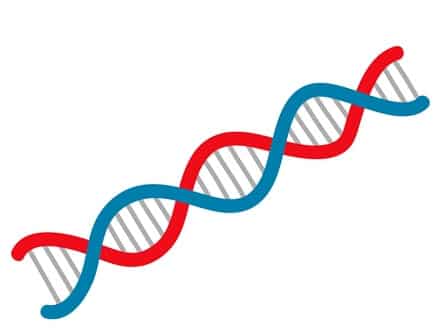
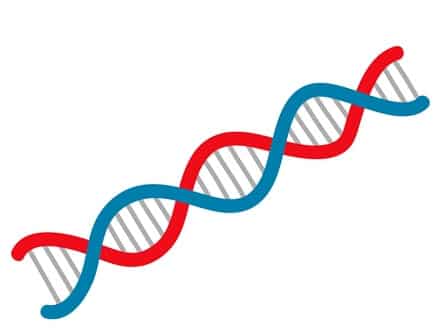
メラニズムは通常、世代から世代へ受け継がれる遺伝子のようです。
マンタのメラニズムの原因となる遺伝子はまだ特定の最中です。
黒化したマンタが特定の場所で多くみられる理由として、「中立進化説・遺伝的浮動」が考えられています。
簡単に言うと、偶然たまたまAという地域にたどり着いたマンタの中に特別な遺伝子があり、それが偶然によって集団に広がっていった結果でしょうか?
研究者は、ジャイアントマンタで表現型と地理的距離間の関連性があることを発見しています。



表現型とは、生物の遺伝的特徴で目で見てわかるもの。
例えば、髪の毛がチリチリだとか、ストレートだとか
マンタの色について|まとめ
マンタの行動範囲は広く、繁殖率の低いマンタを調査することは困難です。
いまだかつて、野生のマンタの出産シーンを見た人もいません。
DNA調査の結果、マンタがマンタ属からイトマキエイ属に変わったように、
遺伝子研究の進歩により、現在の見方が塗り替えされる日が来るかもしれません。
「マンタは食事前や激しい社会的相互作用の間に色を変える」という研究結果もあります。
そうなると、マンタの背中の斑紋やお腹の色をみただけでは、種類の判別すらできなくなります。
マンタのメラニズムは分からないことばかりです。
マンタの遺伝子研究は主にマンタ保護の為に広がっています。
一方、メラニズムのマンタの研究はまだ始まったばかりです。
メラニズムを理解することで、世界中のマンタの繋がりや沢山の謎が分かるような気がします。

